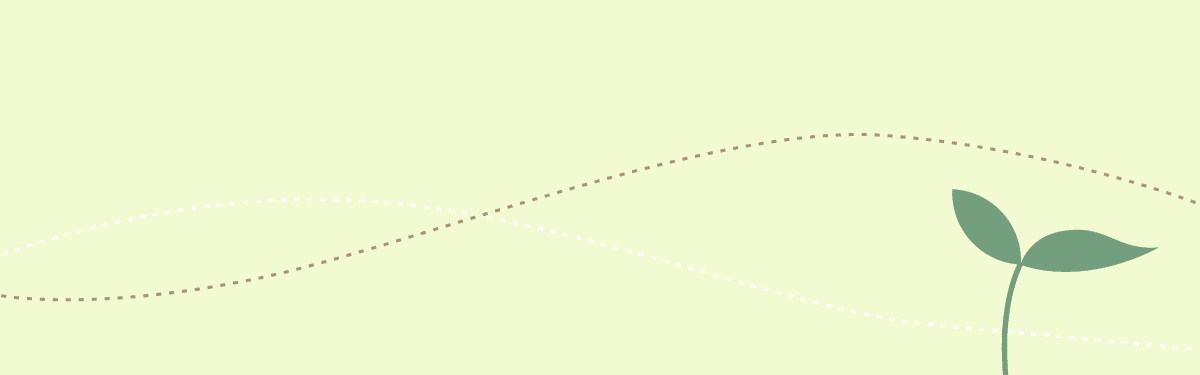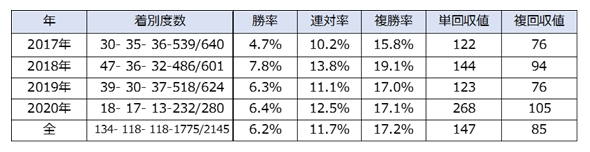あなたは想像したことがありますか?同じ競馬騎手でありながら、収入に10倍以上の差があることを。
中央競馬のトップ騎手であるクリストフ・ルメール騎手は2023年に約3億円を稼ぎました。一方で、地方競馬に所属する多くの騎手たちの年収は300〜400万円程度。中にはアルバイトをしなければ生活できない騎手さえいるのです。
このような現実を知ると、華やかに見える競馬の世界にも、想像以上の「格差」が存在することに驚かされます。危険と隣り合わせの同じ仕事をしているにもかかわらず、なぜこれほどまでの収入差が生まれるのでしょうか?
競馬騎手の収入システムを知れば、その格差の実態が見えてくる

競馬騎手の収入は主に以下の4つで構成されています。
- 進上金(しんじょうきん):賞金の5%が騎手の取り分
- 騎乗手当:レースに出走するだけでもらえる基本報酬
- 調教手当:馬の調教を行った際にもらえる報酬
- その他手当:開催手当やナイター手当など
このうち、最も大きな収入源となるのが「進上金」です。つまり、高額な賞金が出るレースに出走し、好成績を収めることが、騎手の収入を大きく左右します。
ここで驚くべき数字をご紹介しましょう。中央競馬の騎乗手当は2万円〜6万円程度ですが、地方競馬ではわずか数千円。調教手当に至っては、中央が数千円であるのに対し、地方ではたったの数百円というケースもあります。
これはつまり、地方競馬の騎手が生活していくためには、とにかくレースで好成績を収める必要があるということ。しかし、そこにもまた大きな壁が立ちはだかります。
地方競馬の知られざる現実
地方競馬の騎手たちは、早朝から始まる調教、そしてナイターレースが終われば夜10時過ぎの帰宅というハードな生活を送っています。その労働時間の長さと危険度の高さを考えれば、平均年収300〜400万円という数字は驚くほど低いと言わざるを得ません。
特に衝撃的なのは、地方競馬の中でも賞金の低い地域では、5着入賞でもらえる進上金がわずか300円というケースがあったという事実。中央競馬では着外(入賞圏外)でも最低26,000円の騎乗手当が保証されているのに対し、あまりにも大きな差があります。
地方競馬騎手の年収ランキングTOP10から見える実態
それでは、地方競馬でトップクラスの稼ぎを誇る騎手たちの年収を見てみましょう。2023年のデータによると…
- 笹川翼騎手(大井):年収約6,324万円(獲得賞金12億6,481万7,000円)
- 森泰斗騎手(船橋):年収約6,113万円(獲得賞金12億2,272万500円)
- 御神本訓史騎手(大井):年収約4,667万円(獲得賞金9億3,347万9,500円)
- 矢野貴之騎手(大井):年収約4,261万円(獲得賞金8億5,233万7,000円)
- 和田譲治騎手(大井):年収約3,891万円(獲得賞金7億7,830万3,000円)
- 吉村智洋騎手(園田):年収約2,930万円(獲得賞金5億8,615万9,000円)
- 吉原寛人騎手(金沢):年収約2,768万円(獲得賞金5億5,370万7,000円)
- 本田正重騎手(船橋):年収約2,424万円(獲得賞金4億8,493万5,500円)
- 山崎誠士騎手(川崎):年収約2,224万円(獲得賞金4億4,481万円)
- 下原理騎手(兵庫):年収約2,220万円(獲得賞金4億4,412万9,500円)
一見すると、地方競馬のトップ騎手たちも相当な高収入に見えるかもしれませんが、これはあくまで「トップ10」の数字です。大多数の地方騎手たちは、年収400万円以下の厳しい経済状況にあると言われています。
更に興味深いのは、このトップ10の中でも大井や船橋など「南関東の競馬場」に所属する騎手が多いこと。これは地方競馬の中でも、開催地域によって大きな格差があることを示しています。都市部から離れた地方の競馬場ほど、騎手の収入は減少する傾向にあるのです。
衝撃的な中央競馬との収入比較
地方競馬のトップ騎手である笹川翼騎手の2023年の年収が約6,324万円であるのに対し、中央競馬のトップ騎手であるクリストフ・ルメール騎手の年収は約2億9,972万円。その差は4.7倍にも及びます。
更に平均値で見ると、その差は更に広がります。
- 中央競馬騎手の平均年収:約1,000万円(実際はもっと高いという説も)
- 地方競馬騎手の平均年収:約300〜400万円
この差は、騎乗手当や調教手当にも顕著に表れており、同じ「競馬騎手」という職業でありながら、所属する団体によってこれほどまでの待遇差があることに驚かされます。
中央競馬と地方競馬の関係は、しばしば「メジャーリーグとマイナーリーグ」に例えられますが、その収入格差は野球界以上と言えるかもしれません。
切実な現実を物語るエピソード
地方競馬の厳しい経済状況を物語るエピソードをいくつか紹介します。
宮下瞳騎手の奮闘
名古屋競馬場に所属していた宮下瞳騎手は、同じく名古屋競馬場の小山信行騎手と結婚しました。結婚後、宮下瞳騎手はTVで当時の状況を語っています。夫である小山騎手の月収はわずか20万円程度。子供も一人いる中で、生活を支えるために宮下瞳さん自身がアルバイトをして家計を助けていたそうです。
現在、宮下騎手は騎手に復帰し活躍していますが、このエピソードは地方競馬騎手の経済的苦境をよく表しています。
ハルウララ騎乗時の武豊騎手の驚き
連敗続きで有名になった競走馬「ハルウララ」に武豊騎手が騎乗した際のエピソードも忘れられません。このときの高知競馬のレースでは、1着賞金が11万円、5着賞金がわずか6,000円。騎手が受け取る進上金は賞金の5%ですから、5着入賞でもらえる額はたったの300円だったのです。
中央競馬では着外(入賞圏外)でも最低26,000円の騎乗手当がもらえることを考えると、あまりの賞金の低さに武豊騎手自身も問題視していたといいます。
近年の地方競馬の変化と収入改善の兆し
かつて地方競馬は赤字経営が続き、閉鎖に追い込まれた競馬場も少なくありません。そんな暗黒時代を経て、近年は地方競馬の売上も好調となり、徐々に騎手の収入環境も改善されつつあります。
特に南関東の競馬場(大井、船橋、川崎、浦和)では、賞金額も上昇傾向にあり、トップ騎手たちの年収も上がってきています。しかし、それでも中央競馬との格差は依然として大きく、また地方競馬の中でも都市部と地方の競馬場の間には大きな差があります。
地方競馬騎手の収入構造を詳しく紐解く

進上金の重要性
地方競馬騎手の収入の中で最も大きな割合を占めるのが「進上金」です。これは騎手がレースで好成績(通常は5着以内)を収めた際に、賞金の5%が支払われるシステムです。
例えば、賞金1,000万円のレースで1着になれば、騎手には50万円の進上金が入ります。しかし、地方競馬の一般的なレースでは賞金総額が数十万円程度のケースも多く、その5%となるとわずかな金額になってしまいます。
特に注目すべきは、この進上金システムが「勝てる騎手」と「勝てない騎手」の間の収入格差を更に広げる要因となっていることです。実力のある騎手は良い馬に乗る機会が増え、更に進上金を稼ぎやすくなるという好循環が生まれますが、逆の場合は厳しい状況に陥りやすいのです。
騎乗手当の実態
レースに出走するだけでもらえる基本報酬である「騎乗手当」。中央競馬では2万円〜6万円程度支払われるのに対し、地方競馬ではわずか数千円にとどまることが多いです。
例えば、中央競馬の平場(非重賞)レースでも最低2万6,000円の騎乗手当が保証されていますが、地方競馬では場所によって3,000円程度というケースもあります。この差は、1日に複数レースに騎乗する騎手にとって、大きな収入差となって表れます。
また、注目すべきは「着外手当」の差です。中央競馬では入賞圏外(着外)でも一定の騎乗手当が保証されていますが、地方競馬では着外の場合、わずかな騎乗手当しか入らないケースが多いのです。
調教手当から見える格差
馬の調教を行った際にもらえる「調教手当」にも大きな差があります。中央競馬では1回の調教で数千円程度支払われるのに対し、地方競馬では数百円〜千円程度という場合が多いです。
毎朝早くから行われる調教は、騎手の大切な仕事の一つ。その対価がこれほど低いことは、地方競馬騎手の苦境をよく表しています。
また、調教の機会自体も、中央競馬と地方競馬では大きく異なります。中央競馬の調教センターでは多くの馬が集中して調教を行いますが、地方競馬では馬の絶対数が少ないため、調教の機会自体が限られているケースもあります。
開催日数の影響
中央競馬が年間約290日の開催なのに対し、地方競馬は競馬場によって開催日数が大きく異なります。南関東の競馬場では年間100日以上の開催がありますが、地方の小規模な競馬場では年間数十日程度の開催にとどまる場合もあります。
開催日がない日は、基本的に騎乗手当や進上金といった主要な収入源がなくなり、調教手当だけが頼りになります。この開催日数の差も、騎手の年収に大きな影響を与えているのです。
地方競馬の中の格差:南関東と地方の差
南関東(大井・船橋・川崎・浦和)の優位性
地方競馬の年収ランキングを見ると、上位を南関東の競馬場(大井・船橋・川崎・浦和)に所属する騎手が占めています。これは偶然ではなく、以下のような要因があります。
- 賞金額の差:南関東の競馬場は、他の地方競馬場に比べて賞金額が高い傾向にあります。特に大井競馬場の「東京大賞典」などのG1レースでは、1億円以上の賞金が設定されることもあります。
- 入場者数・売上の差:首都圏に位置する南関東の競馬場は、人口密集地にあるため入場者数も多く、売上も高い傾向にあります。これが賞金額の高さにも反映されています。
- 開催日数の差:南関東の競馬場は年間を通じて多くのレースが開催されるため、騎手の出走機会も多く、結果として収入増につながります。
これらの要因により、同じ「地方競馬騎手」でも、南関東と地方の小規模競馬場では年収に大きな差が生まれているのです。
地方小規模競馬場の苦境
高知・佐賀・笠松・名古屋などの地方小規模競馬場では、以下のような厳しい状況があります。
- 賞金額の低さ:重賞レースでも賞金総額が数百万円程度というケースも珍しくありません。
- 馬の質の差:一般的に、レベルの高い競走馬は賞金の高い競馬場に集まる傾向があります。そのため、地方の小規模競馬場ではレベルの高い競走馬が少なく、レースの質や注目度にも影響します。
- インフラの差:設備や環境面でも、都市部の競馬場と地方の競馬場には大きな差があります。
これらの要因が複合的に作用し、地方小規模競馬場に所属する騎手の収入は更に厳しいものとなっているのです。
地方競馬騎手の昔と今:変化する環境

インターネット投票の普及による好影響
かつての地方競馬は、場外馬券売り場や競馬場での現地購入が主な売上源でした。しかし、インターネット投票の普及により、全国どこからでも地方競馬の馬券を購入できるようになり、売上は大きく改善しました。
特に2020年以降のコロナ禍では、中央競馬が一時休止する中、地方競馬が継続して開催されたことで新たなファン層を獲得。この流れは、賞金額の増加や騎手の収入改善にもつながっています。
メディア露出の増加
近年はSNSの普及もあり、地方競馬の魅力が再評価されています。特に南関東のナイター競馬は「ナイスナイト」などの愛称で親しまれ、若い世代の間でも人気を集めています。
テレビ番組やYouTubeなどのメディアでも地方競馬が取り上げられる機会が増え、これが売上増につながり、間接的に騎手の収入環境改善にも寄与しています。
女性騎手の活躍
宮下瞳騎手をはじめとする女性騎手の活躍も、地方競馬の新たな魅力となっています。かつては男性中心だった競馬界でも、女性騎手が着実に実績を積み上げ、注目を集めています。
このような多様性の拡大は、地方競馬の新たなファン層開拓につながり、業界全体の活性化に貢献しています。
騎手という職業の魅力と課題
命がけの仕事がもたらす独特の職業観
騎手は、時速60kmを超えるスピードで馬を操る、文字通り「命がけ」の仕事です。落馬による怪我や最悪の場合は命を落とすリスクと常に隣り合わせの世界で、彼らはなぜ騎手という道を選ぶのでしょうか。
多くの騎手が語るのは「馬への愛」や「勝負への情熱」です。金銭的な報酬だけでは測れない、競馬ならではの魅力が彼らを支えています。しかし、そうした熱意だけでは生活できない現実があることも忘れてはなりません。
10代から始める厳しい修行
騎手になるためには、10代の若さから厳しい修行を積む必要があります。JRAの騎手課程や地方競馬の養成所で学び、デビューを果たしても、すぐに勝てるようになるわけではありません。
こうした長い下積み期間を経て一人前になる職業だからこそ、最低限の経済的保証があるべきではないでしょうか。現状では、才能があっても経済的な理由から騎手を断念せざるを得ないケースもあると言われています。
キャリアパスの課題
騎手としてのキャリアは、体力的な問題もあり比較的短いと言われています。特に地方競馬の騎手は、収入の少なさから若いうちに引退するケースも少なくありません。
引退後のキャリアパスも大きな課題です。一部の有名騎手は調教師に転身したり、メディアで活躍する道もありますが、多くの騎手にとって引退後の道は険しいのが現実です。
まとめ:競馬界の未来と騎手の待遇改善に向けて
地方競馬の騎手たちは、厳しい経済環境の中でも情熱を持って競馬界を支えています。彼らの存在があってこそ、私たちは競馬を楽しむことができるのです。
近年は地方競馬の売上も回復傾向にあり、騎手の待遇も少しずつ改善されつつあります。しかし、中央競馬との格差、そして地方競馬内での格差はまだまだ大きく、改善の余地は十分にあります。
競馬ファンとして、地方競馬の魅力を再発見し、その存在価値を高めていくことが、結果的に騎手たちの待遇改善にもつながるでしょう。地方競馬の魅力は、中央競馬とは異なる独自の個性にあります。その魅力を多くの人に知ってもらい、地方競馬を盛り上げていくことが、騎手たちへの最大の応援になるのではないでしょうか。
落馬など時には命にかかわる危険と隣り合わせの職業でありながら、年収面での厳しい現実に直面している地方競馬の騎手たち。彼らの奮闘に感謝の気持ちを持ちつつ、競馬界全体がより良い方向に発展していくことを願ってやみません。